このページでは「ルーペの使い方」「理科におけるスケッチの仕方」について解説しています。
ルーペやスケッチの動画による解説は↓↓↓
チャンネル登録はこちらから↓↓↓
※顕微鏡の使い方はこちら →【顕微鏡の使い方】←
1.ルーペの使い方
・ルーペは目に近づけたまま離さない。
・ピントが合わない時はルーペを目に近づけたまま観察したいものを動かす。
・観察したいものが大きいときは自分が動く。
・目を傷めるので絶対に直接太陽を見てはいけない。
ルーペの使い方の基本は、目から離さないということです。
小さいもの(手に持てるサイズ)を観察しているときは、手で観察物を動かしてピントを合わせましょう。
大きいもの(手に持てないサイズ)を観察しているときは、ルーペを目に当てたまま自分が前後に動いてピントを合わせましょう。
その際に、太陽を直接見ることだけは絶対にやめましょう。
2.理科でのスケッチの仕方
理科では観察したものをスケッチして記録に残すことがあります。
その際、気を付けなければならないことを挙げておきます。
細い線と小さい点で、見たものを正確に書きます。
できるだけとがった鉛筆を使いましょう。
反対に次の①~③のようなことは気を付けておかなければなりません。
①影はつけないこと。
②線を重ねて二重書きはしないこと。
③観察物以外のものが書かないこと。
例えば次のスケッチはよいスケッチと言えるでしょうか?
実はあまり良いスケッチとはいえません。
↓のように、改善した方が良い点があります。
特にルーペや顕微鏡をのぞいたときの”ふち”(丸い部分)は書く必要がありません。
観察しているものだけを正確に書く、というのが原則です。
その他にも観察した日の日付や気温、湿度や気づいたことなどがあればメモしておきましょう。
以上はあくまでも理科のスケッチの仕方です。
美術や図工ではまた異なるので気を付けましょう。
※顕微鏡の使い方はこちら →【顕微鏡の使い方】←

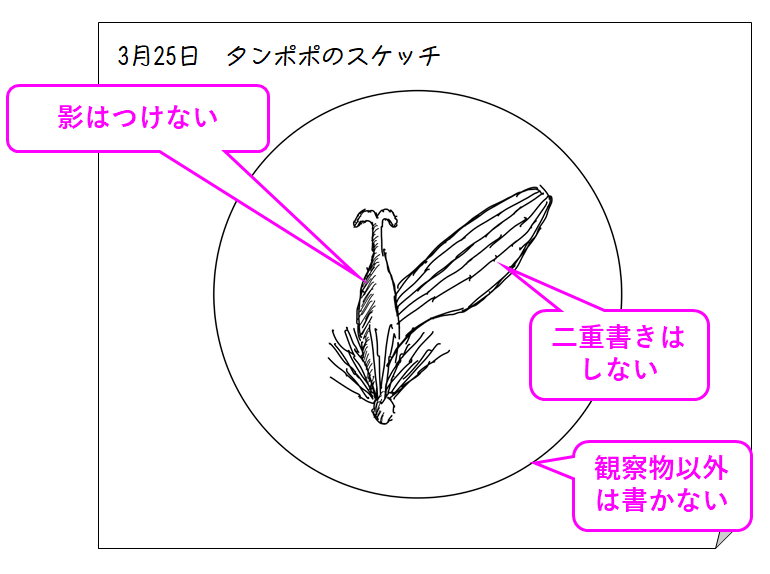

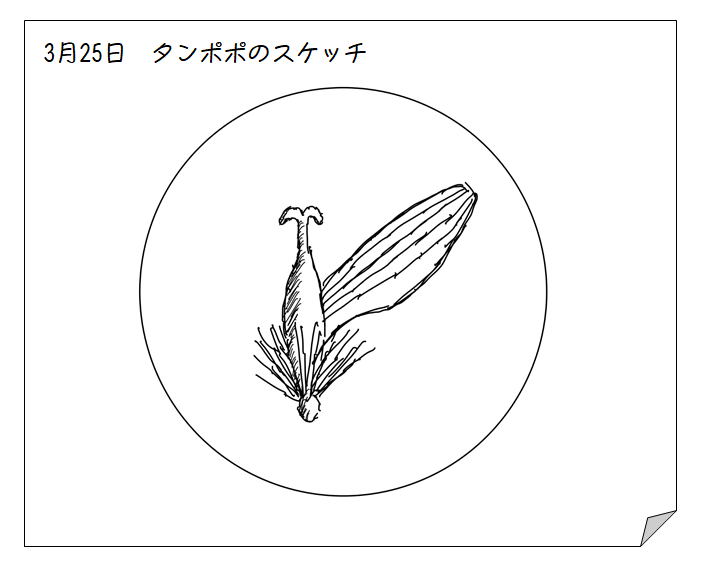
コメント(承認された場合のみ表示されます)