このページでは「春分・秋分・夏至・冬至の日の各季節の太陽の日周運動」について解説しています。
動画による解説は↓↓↓
チャンネル登録はこちらから↓↓↓
1.南中高度の公式
春分(3/20ごろ)・秋分(9/20ごろ) = 90°-x°
夏至(6/20ごろ) = 90°-x°+23.4°
冬至(12/20ごろ) = 90°-x°-23.4°
※x°は観測地点の北緯とする。
※また地軸が公転面の垂直方向に対して23.4度傾いているとする。
※公式の導出方法は→【南中高度の公式】←を参照。
この公式から北半球での太陽の南中高度は
春分・秋分の日を基準として
夏至 → 春分・秋分よりも23.4度高い
冬至 → 春分・秋分よりも23.4度低い
ことがわかります。
2.季節による太陽の動き
以下では北半球での太陽の動きを考えます。
春分・秋分の日
先ほどの「太陽の南中高度の公式」と「北極星の高度=その土地の北緯」より
↓のように太陽の動き(日周運動)は示されます。
※→【北極星の高度】← / →【太陽の日周運動】←も参照。
このときの太陽の動き(日周運動)は
真東で日の出→南中→真西で日の入り
という動きです。
夏至の日
先ほどの「太陽の南中高度の公式」より
「夏至の日の太陽の南中高度」は「春分・秋分の日」に比べると23.4度高いです。
それを図に示しましょう。(↓の図)
太陽は地軸を中心に日周運動をしています。
その様子を書き記すと
北半球における夏至の日の太陽の動きは↓のようになります。
冬至の日
先ほどの「太陽の南中高度の公式」より
「冬至の日の太陽の南中高度」は「春分・秋分の日」に比べると23.4度低いです。
それを図に示しましょう。(↓の図)
ここで太陽は地軸を中心に日周運動をしています。
その様子を書き記すと
北半球における冬至の日の太陽の動きは↓のようになります。
四季の太陽の動き
これまでのそれぞれの季節の太陽の動きをまとめると↓のようになります。
これを天球全体で考えた図が↓です。
さらにこれを横から見た図が↓です。
ここに角度の関係性も書き足してみましょう。
※あくまでこれは「北半球」から見た太陽の動きです。赤道や北極や南極、南半球では異なりますよ。
この図から太陽の動きについて↓のようにまとめることができます。
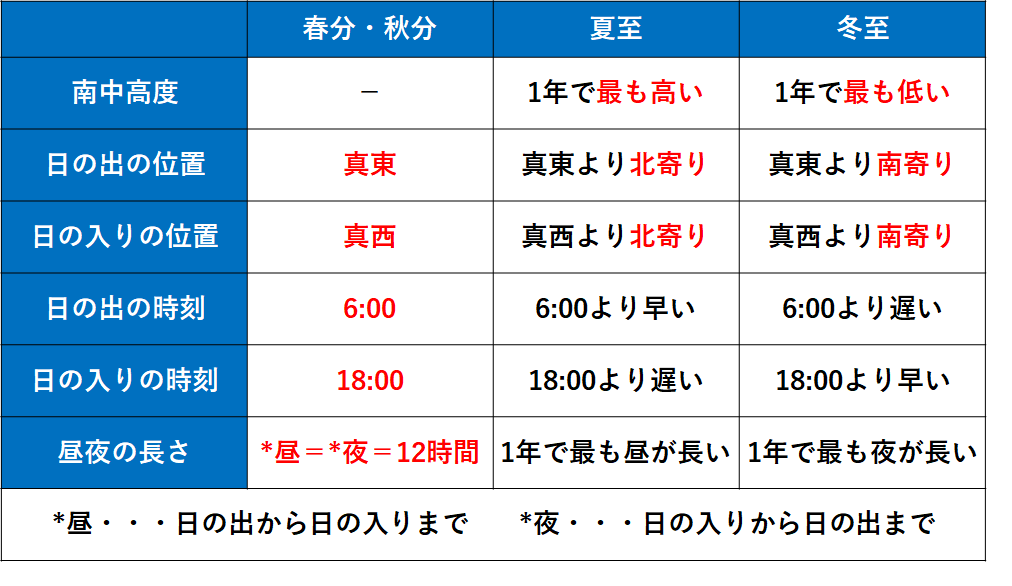
*特に日の出、日の入りの方角のちがいを押さえておこう。
また南中高度の違いから
なぜ「日本の夏は暑いか」「日本の冬は寒いか」を考えることもできます。
それは一定面積あたりに受ける「太陽からのエネルギー」の量が夏至の日>冬至の日となっているからです。(↓の図)
POINT!!
・天球上で、各季節の太陽の日周運動の道筋は異なってくる。
・夏至、冬至の日の出、日の入りの方位を押さえよう。
・季節による太陽からのエネルギーの受け取り方の違いを押さえよう。

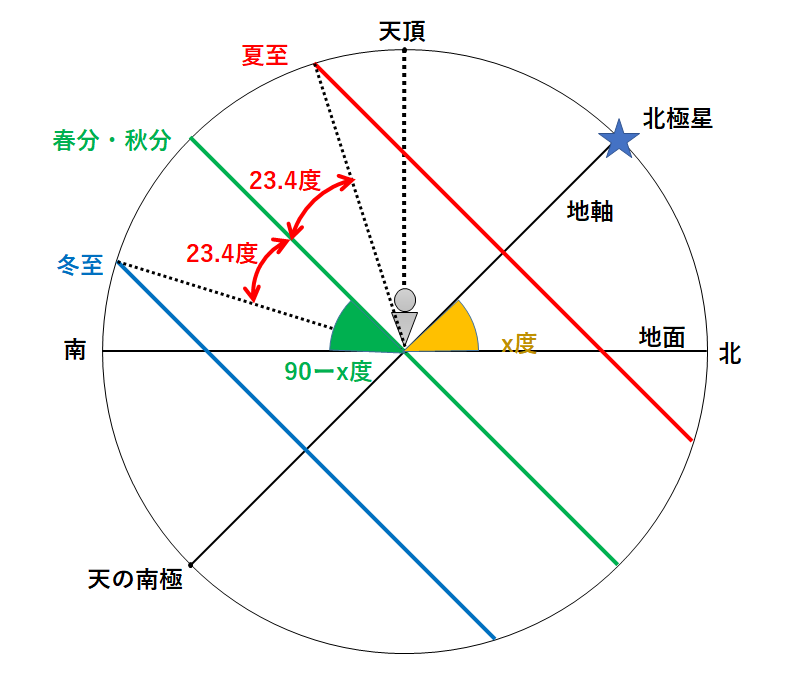
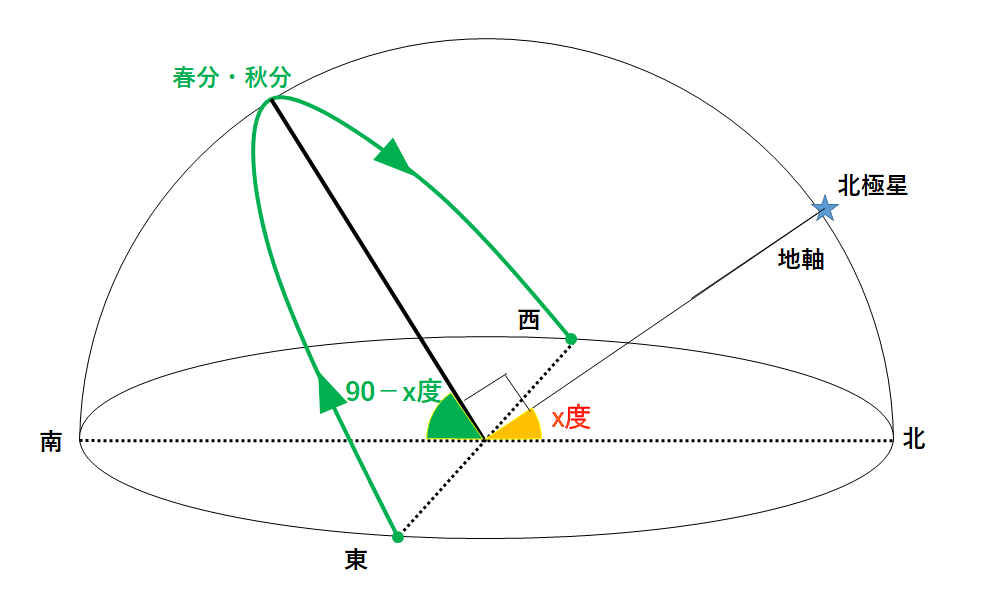
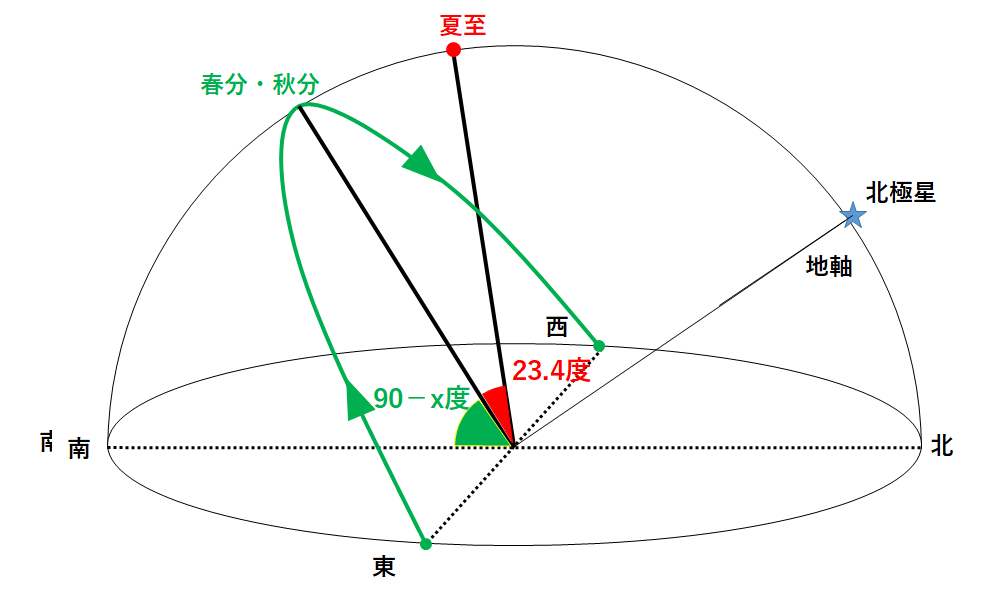
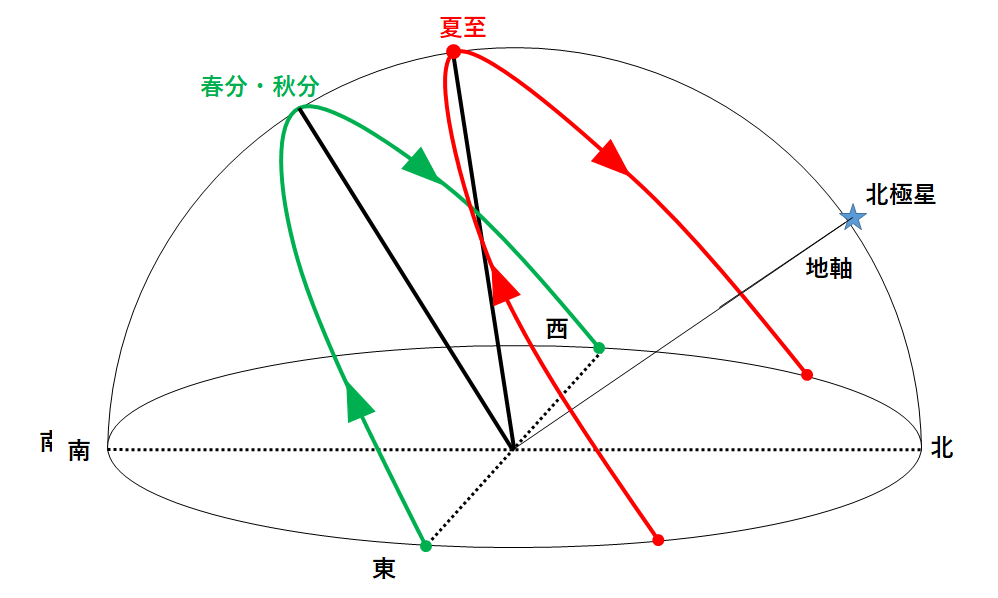
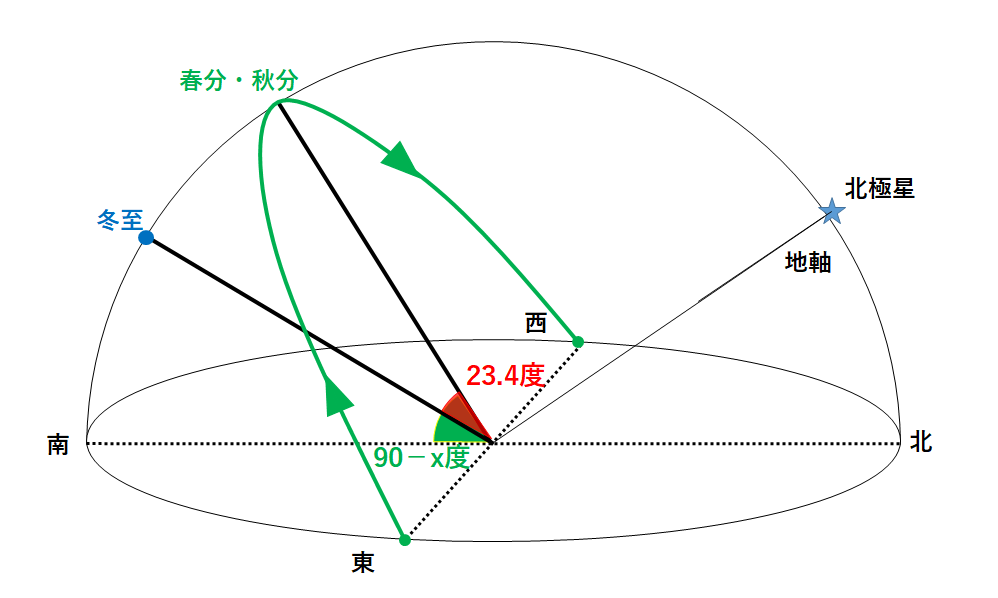

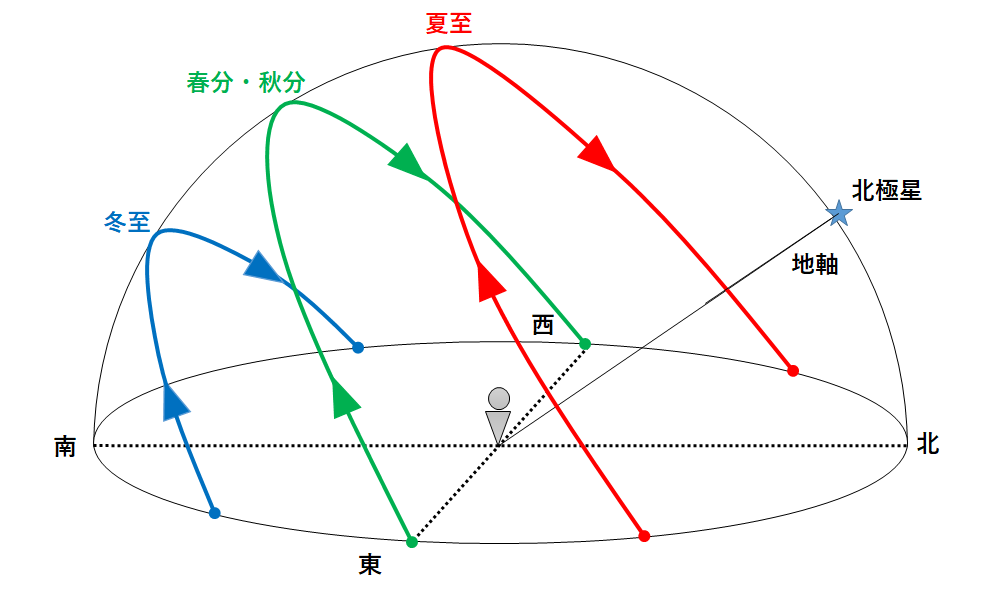
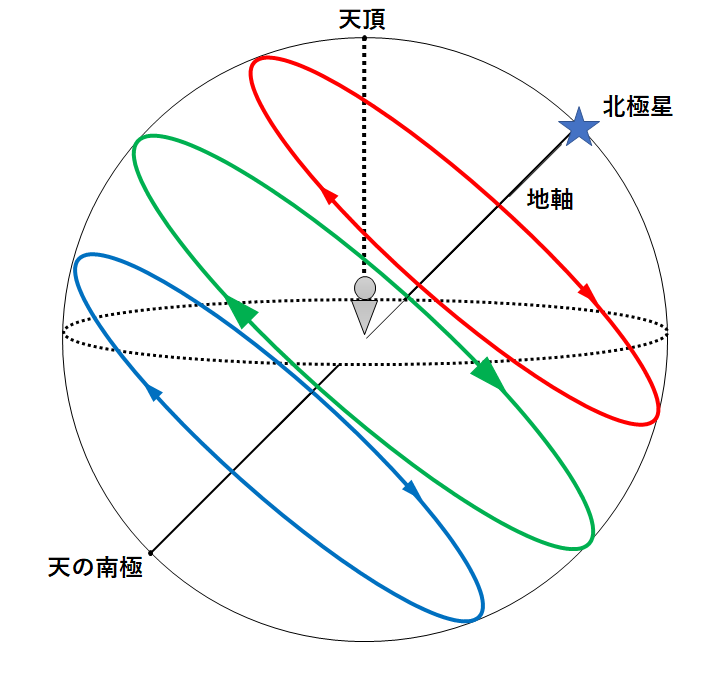

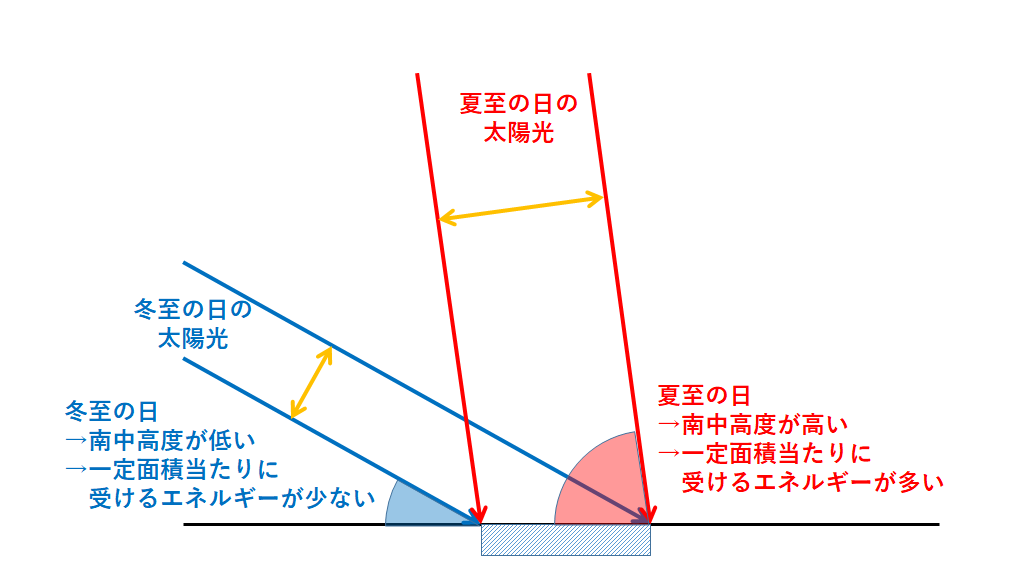
コメント(承認された場合のみ表示されます)
[…] (https://chuugakurika.com/2017/12/07/post-964/ ←管理者さまよりご了承いただき、こちらのページより画像をお借りしました。ありがとうございます。) […]