このページでは「背骨のない動物(無せきつい動物)」「節足動物」「軟体動物」について解説しています。
せきつい動物については→【せきつい動物】←を参考に。
動画による解説は↓↓
チャンネル登録はこちらから↓
1.無せきつい動物
背骨(=せきつい)がない動物。
せきつい動物より多い種が存在する。
基本的には卵生・変温動物が多いが、無性生殖をおこなうものも存在する。
※無性生殖については→【無性生殖】←を参考に。(中3の学習内容です)
中学段階では次の3種類に分類できるようにしておこう。
・節足動物・・・あしに節がある。
・軟体動物・・・内臓が外とう膜でおおわれている。
・その他・・・・環形動物・海綿動物・輪形動物など。
2.節足動物
あしに節がある。※関節のようなものをイメージしよう。
からだが丈夫な殻でおおわれている(外骨格という)。
昆虫類・甲殻類・クモ類・多足類の4種類に分かれる。
卵生・変温動物である。
胸部には3対(計6本)のあしがある。
腹部と胸部にある気門で呼吸をしている。
(例)バッタ・モンシロチョウ・カブトムシ・アリなど。
※クモは昆虫ではないので注意!
からだが頭胸部と腹部の2つに分かれている。(頭部・胸部・腹部の3つに分かれているものもいる)
頭胸部には5対(10本)のあしがある。
水中で生活するものが多いので、えらや皮膚で呼吸をしている。
(例)エビ・カニ・ザリガニ・ミジンコ・ダンゴムシなど。
※特にミジンコ・ダンゴムシが間違えやすいので注意!
あしがたくさんある。
(例) ムカデ・ヤスデなど。
3.軟体動物
あしに節がなく、筋肉でできている。
内臓は外とう膜でおおわれている。
ほとんどがえら呼吸をしている。
卵生・変温動物である。
(例) イカ・タコ・マイマイ・ナメクジ・アサリ・クリオネ
※マイマイとはカタツムリのこと。
※イカ&タコ&カタツムリ&貝のなかまと覚えておきましょう。
4.その他の無せきつい動物
無せきつい動物は非常にたくさんの種類が存在します。
そのすべてを覚える必要はありません。
その他にあてはまるものとして
ウニ・ヒトデ・ナマコ・クラゲ・イソギンチャク・ミミズ
などがあります。
これらは軟体動物であると間違えやすいです。
軟体動物ではないということを覚えておくことが重要です!
POINT!!
・節足動物の特徴は「外骨格」「あしに節がある」の2つ。
・軟体動物の特徴は「外とう膜がある」こと。
・節足動物の中でも昆虫類・甲殻類をよく覚えておこう。
・軟体動物の代表例を覚えておこう。
・ウニ・ヒトデ・ナマコ・クラゲ・イソギンチャク・ミミズは節足動物でも軟体動物でもない、ということを覚えておこう。
こちらもどうぞ
せきつい動物の分類や無せきつい動物・進化の暗記ドリルを販売中。
1つ220円(税込)です。こちらからどうぞ。

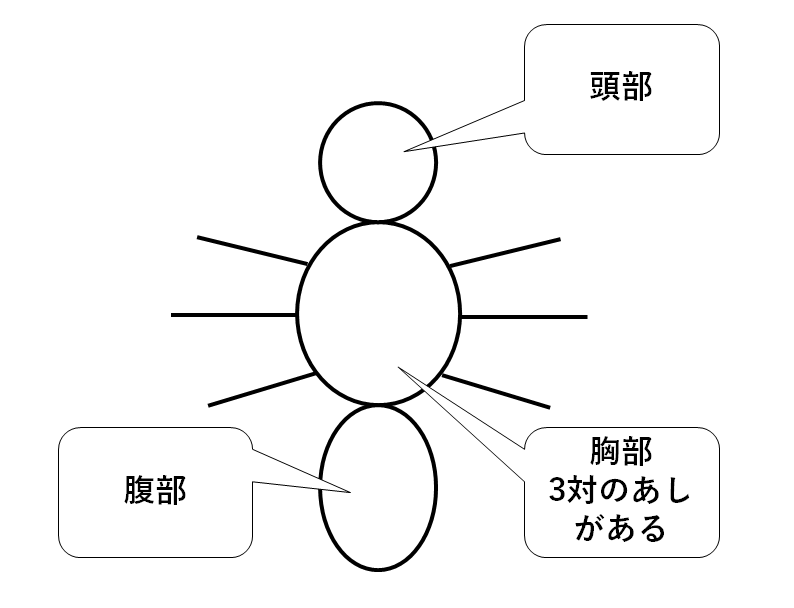
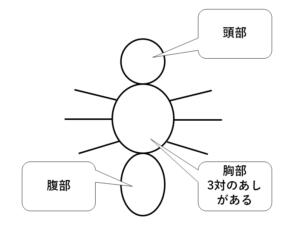
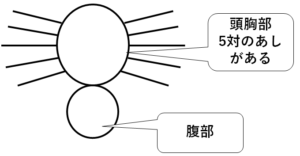
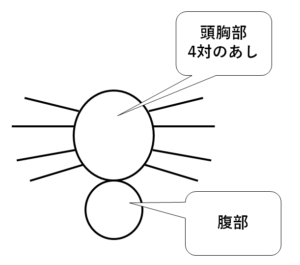
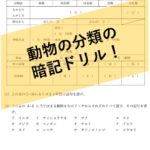

コメント(承認された場合のみ表示されます)
お願いします
さとう様
コメントありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
何かあればまたご覧ください。
このサイト本当に助かりました!
ありがとうございます!
Marumaru様
コメントありがとうございます。
お役に立てて何よりです。またぜひご利用ください。
すごく助かりました!
これからもちょくちょく利用させて
いただきます。
作業がはかどって、すごく良かったです!!
本当に感謝✌
さとう様
コメントありがとうございます。
お役に立てているようで嬉しいです。
いつでも利用してくださいね。
理科の期末テストに出そうな問題教えてくださいby中学1年
ともきゅん様
学校の先生によるので何とも言えませんが、
・節足動物の特徴→あしに節がある・外骨格におおわれている
・昆虫類はからだが頭部・胸部・腹部に分かれている
・甲殻類の代表例→ミジンコが聞かれやすい
・軟体動物の特徴→内臓が外とう膜におおわれている
この辺りはよく出題されます。
当たり前のことなのにいちから
丁寧に教えてくださってありがとうございました。
すごい㎘様
コメントありがとうございます。
ご理解のお役に立てたなら幸いです。
またいつでもご活用ください。
とてもわかりやすくてよかったです
s.t様
コメントありがとうございます。
お役に立てたなら幸いです。
またいつでもご活用ください。